今年も一級建築士製図試験の日が迫ってきました。私はR6年度の一級建築士製図試験に角番合格し、晴れて一級建築士になりました。今回は、そんな私の合格までの道のりや勉強法について、お話ししていきます。
R4年度学科試験ストレート合格!
R4年度学科試験の結果は以下の通りです。
計画…14/20点、環境・設備…16/20点、法規…27/30点、構造…21/30点、施工…13/25点
合計…91/125点
合格基準点+1点での合格でした。特に苦手な施工では足切りギリギリ。あまりの不正解の多さに、泣きそうになりながら自己採点したのをよく覚えています。
学科試験の勉強は、日建学院で前年の二級建築士製図試験が終わった直後から始めました。ひたすらに過去問を繰り返し解いていたように思います。
合格するためのコツは、4択から正答肢を見つけられるようになることではありません。ズバリ、正誤を確実に判断できる選択肢の数を増やすこと!
建築士試験で過去問が重宝されているのは、過去問からの出題が非常に多いからです。ただ、新規の出題が全くないわけではありません。さらには、過去問を捻った応用問題も近年よく出題されます。そういった問題に遭遇した時、最後は勘に頼ることになりますが、いかに選択肢を減らせるかで正答率を上げることができます。
おすすめの勉強法は、過去問を問ごとではなく、選択肢ごとに取り組む方法です。普通問1、問2、…と解いていくと思いますが、これだと偶然正答肢が覚えている内容だった場合、それ以外の3肢がきちんと暗記できているか判断できません。そのため、各問の選択肢①だけを一問一答形式で解いていきます。次に選択肢②だけ、選択肢③だけといった流れです。曖昧に覚えている選択肢をなくすことで、正答率が上がり、新規の問題が混ざっても対応できます。同じ過去問5周でも、勉強の仕方で本試験での対応力がかなり変わってくるので、これから学科試験に臨む人はぜひやってみてください!
R4年度製図試験「事務所ビル」ランクⅢで惨敗…
学科合格をした年の製図試験はランクⅢで惨敗でした。
時間内に書き上げることはできたものの、初出題だった杭基礎が正しく描けずおそらく大きな減点になったと思います。他の初出題項目だった階数自由、延べ面積指定なしには対応できたから、余計に悔しくて一級建築士試験の難しさを感じました。
作図のスピードを速くするにはとにもかくにもトレースだと思います。学校の課題や過去問の解答例を自分のエスキスに書き直して、そこからできれば通しで作図に取り掛かります。あまり頭を使わずにできるので、初めの頃の何を暗記していいかも分からない時にやっておいて損はありません。
R5年度製図試験「図書館」ランクⅣの不完全燃焼
令和5年度の製図試験、満を持して受験したにもかかわらず、結果はランクⅣでした。
2年目も最後まで完成はさせられたものの、試験中も「このプランでいいんだろうか…」「本当に意図を組んだ建物になってるのか?」と不安になりながらの戦いでした。昨年度以上に自由度が高く、空間構成に意味を持たせるのが非常に難しかったです。今回も初出題の北側斜線は日建学院の直前対策で学習済みだったので対応できましたが、何が原因でランクⅣだったのかは今もわからないままです。
2年目も日建学院に通い、1年目の短期間では網羅しきれなかった基礎的な知識を幅広く学びました。特に記述については、付け焼刃で挑んだ1年目と比べると格段に自分の言葉で解答できるようになり、自信がつきました。記述はある程度は過去問の暗記で対応できるものの、正確な知識をインプットしておくことで、応用問題に対応したり、文章量の不足を回避することができます。同じような問題でも、質問内容の微妙な違いや解答欄の大きさによって、解答をカスタマイズできるように、解答のバリエーションを増やしておくことがポイントだと思います!
R6年度製図試験「大学」初出題の課題で合格!
追い込まれた3年目、R6年製図試験でランクⅠ!ついに合格することができました。
試験制度の問題だけではなく、私生活も考慮して一級建築士への挑戦自体を最後にしようと思って臨んだ角番受験でした。7月の課題発表で「大学」という過去に例がないテーマを見たときは、とんでもない試練だと思い、呆然としてしまいました。ただ本試験を終えると、課題文から予想できた免震構造や過去問からの類似問題が多く、迷走することなく素直に解答できた気がします。近年は敷地の周辺環境がかなり複雑になっていますが、知り合いの合格者の解答を見ると、法令違反でなければアプローチ等の解釈は大きな減点対象ではなさそうです。自分なりの解釈や設計意図を明確にすれば問題ないというのが個人的な見解です。
3年目は思い切って資格学校を日建学院から総合資格に変更しました。通う学校も最寄りの学校ではなく、生徒数の多い都会の学校を選択しました。理由は、大きく2つあります。1つ目は、最寄りの学校だと通いたいコースや曜日が生徒数不足で開講されないこと。2つ目は、本試験は相対評価だから、他の受験者のレベルを把握することが必要だと思ったこと。
1 地方あるある!通いたいコースや曜日が制限される
私が住んでいる県は地方で、希望しているコースが生徒数不足で開講されないということがよくあります。特に私は仕事が平日休みだったので、土日休みの人と比べると選択できるコースがかなり制限されてしまいました。悩ましいのが、申し込みをする段階で、コースが開講される保証がないこと。「水曜コースが開講されなかったら日曜コースか通信講座で受講してください」と言われ、実は2年目は課題発表のある7月までを通信講座で受講していました。私の場合は、通信講座だとモチベーションを維持できず、残念な結果になってしまいました。3年目は電車で片道1時間かかりますが、半年間ほとんど毎週通学していたので、モチベーションが途切れることなく課題に取り組めました。移動時間がもったいないと思われるかもしれませんが、私にとっては息抜きになり、ちょうどよかったのかもしれません。
2 ライバルの存在の大切さ!自分のレベルを意識しながら課題に取り組める
都会の学校に通い始めて、一番衝撃だったのが生徒数の多さです。例年人数が少なめの水曜コースとはいえ、私が通っていたクラスは生徒数が15人ほどいました。毎回の講義で交換採点をしたり、グループワークでお互いの図面を評価し合える環境というのが、新鮮で非常に恵まれていると感じました。実は不合格だった年に通っていたクラスの受講生は3~5人程。その中に初受験はもちろん、製図自体が初めてという人もいました。講義で最後まで図面を完成させられるのが自分だけということも多く、知らず知らずのうちに安心してしまっていたのかもしれません。
教育的ウラ指導の「一級建築士受験 合格者たちの勉強法」でも製図試験の勉強法では、他の受験者の図面を研究することが大切だと述べられています。過去の合格者の図面はもちろんですが、不合格者の図面からも学べることは多くあります。採点者の立場になって、他の受験者と自分の図面を相対的に評価することが合格への大きな近道だと思います。製図試験で苦戦している人は、ぜひ意識してみてください!

さいごに
ここまで私の一級建築士試験合格までの道のりを読んでくださりありがとうございました。
一級建築士は合格難易度の非常に高い国家資格です。私は合格まで3年かかりましたが、人によってはスムーズに取れていて羨ましいと思うかもしれませんし、そんなに合格まで時間がかかるのかと驚かれた方もいるかもしれません。個人的には、3年で終わってよかったと安心しています。それでも3年間紆余曲折ありながら挑戦した経験はそれだけでかけがえのないものだったと思います。この経験が、これから一級建築士を目指す人や現在挑戦してる人の支えになれば嬉しいです。


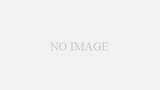
コメント